|
| 歌のはなし |
曲名 |
公表作品 |
作詞者 |
作曲者 |
| 075 |
地下書店 |
地下書店
|
糸田ともよ
|
及川恒平 |
|
|
|
|
(1)
A F#m Bm7 E7
たそが れの 地下書店-に いっつうの メールが届 く
A F#m Bm7 / F#m A
多分 もう 行かないと い う 夢の つづき 短い言 葉
D F#m G / Gmaj7 A
ほつれ た つばさ は 知らな い 本 の
Bm F#m Bm7 / C#7 F#m D7
しおり に 使っ-て 遠い棚に も ど す
(2)
A F#m Bm7 E7
階だ んを 数えて登 る ありふ れた 癖だとして も
A F#m Bm7 / F#m A
目のま えの たった一段 崖だったら 数えられな い
D F#m G / Gmaj7 A
なにげ なく つばさ を 捨て た けれ ど
Bm F#m Bm7 / C#7 F#m D7
残っ た ひとつ は このま ま 忘 れた い
(3)
A F#m Bm7 E7
抱きあ えぬ うおの姿-で 巡り会い はぐれるま で
A F#m Bm7 / F#m A
祝ふ-くの 雨の拍手に わるぎもなく 耳をふさい だ
D F#m G / Gmaj7 A
つめた く しびれ た うお の 尾ひれ が
Bm F#m Bm7 / C#7 F#m D7
まぼろ しでもつばさ に 変われ ば 重 い
☆
A F#m Bm7 E7
たそが れの 地下書店-に いっつうの メールが届 く
A F#m Bm7 / F#m A
多分 もう 行かないと い う 夢の つづき 短い言 葉
|
|
|
歌のはなし、今年最後のページ更新はこのSONGにしよう。
秋に出来たSONGである。
それからもう何度もライブで歌ってきた。
聞き手にどう受け止められているのか、気にならないわけではないが、
このSONGは、それ以前に、届いてほしいという願いがすである。
もっと、じこちゅーに言えば、届かないんだったら仕方がない、
といったところか。
こんな、わがままが、必ずしも、いつも成立するわけもない。
それどころか、空振りに終わる確率はひくくないだろう。
そうして、このSONGは空振りに終わっていない。
こうも声高に言い放つのには、もちろん訳がある。
ソウデス、作者の糸田さん本人に、イイデス、
と言ってもらえたからなのだっ。
さて、ここまではいい。
順風満帆の船出と言ってもいい、新人にしての開幕投手かもしれない。
だが、その先、相手選手たちの研究を上回る成績を残していく実力が、
はたしてあるのかどうか。
SONGといえども、いずれ独り立ちして歩んでいかねばならない。
有能な作家、シンガーの手になったとき、
SONGが、そうなる確率は高くなる。
そうして、時代にふれる編曲がほどこされたとき、それは一層高くなる。
ところが、ぼくの作戦は、
かならずしも、そのセオリーを受け入れているのでもない。
まず、作者、糸田ともよの世界を第一義とする。
その結果、
時代と触れあうための、言葉をあえて選択するということは、しない。
本音を言えば、この「地下書店」というSONGには、
すでにそんな時代性が、
つまり、ポピュラリティが含まれていると、思っている。
これは、ここにある「ポピュラリティ」を、
音楽を聴くがわで発見してください、
と開き直っているのにほかならない。
ぜんぜん、カワイクナイのである、きらわれるのである。 |
|
 |
が、しかし作者や歌い手がきらわれても
耳に残るSONGはあるだろう。
まだ、言っている・・・。
やがて、そのSONGの周辺域までふくめて、
あたかも事実のように容認されていく風景を、
ぼくらは、何度も目撃してきたではないか。
なにも、フォークソングだけの話ではない。
なにも、音楽だけの話でもない。
そう、なにも文化の話ばかりでもない。
そうやって、「史実」が積み上げられていく様を、
僕の生きながらえてきた、
わずか五十数年の間にも充分に目撃している。
さて、そこで。
ぼくも、そのおんけいにあずかりたいと、虎視眈々と狙っているわけだ。
と、家庭の事情はこれぐらいにして、このSONGの説明。
まず、糸田ともよの歌集「水の列車」から、
この「地下書店」に拉致したことばを含む歌を数首、あげてみる。
各歌の末尾の( )内は「水の列車」中の章の題名である。 |
|
 |
| 階段を数えてのぼる癖 死後も 黄昏いろの地下書店から (幻影肢) |
| 受話器の声しばし途切れて 雪の音 あるいは翼を片づける音 (水の列車) |
| 信号機の充血した眼に疎むまま時代(とき)は流れて見知らぬ街角 (幻想烽火) |
| 抱きあえぬ魚の姿でめぐりあう驟雨の拍手に拉ぐ水駅 (幻想烽火) |
| 階段のひとつ断崖 踏みはずし縋れば神のネクタイは瀧 (水の列車) |
|
 |
糸田ともよ「水の列車」より、
このSONGに直接あらわれたことばを含む作品群である。
むろん、この歌集の全体からさまざまなインスピレーションを受けて、
SONG「地下書店」になっていった。
あらためて言う必要もないだろうけれど。
ぼくが、
これらのことばを使ってSONGとして成り立たせようとしたとき、
かなり意識的に選択、あるいは、こだわったことがある。
それは、このSONGの聞き手の思い描く場所は、
街の中であってほしいということだった。
その訳をここに書くのが順番というものだけれど、
実はぼく自身が、そのあきらかな理由がわかっていない。
ただ、このSONGを歌っていく中で、
やがてわかってくることがワカッテイル。
みょうに、そんな自信があるのだ。
単に、ヒトがわのためと言うよりも、
このSONGが独り歩きしはじめる時がきたとして、
そのほうが、かわいがってもらえそー、ということかなあ。
親が生まれてくる子供の名前を、考える気持ちと重なるのだろうか。
なにか習い事をさせて、
きょうよーを身につけさせようという熱意とダブるのだろうか
と、想像しててはみるが、実際のところ、まだわからない。
あっ、
このあたりの親ゴコロは、すでに糸田ともよのことばを第一義とする、
と、気どって言い放ったのを、忘れているのか・・・。
どうせならもっと、気の利いたいいぐさを考えるのだったな。 |
|
 |
SONGには歌い出しに、まるでスキーのジャンプ競技のような、
飛距離を感じさせるものがあり、
このSONGは、その種の分類に入りそうだと思った。
最初に歌ったときにすぐ思った。
ぼくの小さな経験でいうと、
「面影橋から」というフォークソングが、それだった。
あとで、すこしずつ、ああ、じつは飛距離があったのですね、
と訂正されていくSONGもあるから、
今ありそうだからなんだというのではないが。
ないよりはいいか、とした上で、
かつ飛型点が高ければ文句ないのだけれど、
この飛型点というやつは、それこそ、主観の問題もふくまれたり、
なかなか絶対というわけにもいかないので、やっかいだ。
飛距離と言ってみたこの感覚は、
かならずしも、だからいい歌はすべてこうだというのではないが、
説明は必要だ。
たとえば、シャンソン・ド・フランセの中には、
イントロ部分、音程間のあまりない、
ほとんど台詞状態で入ってくる名曲がある。
そのまま、エンディングまで、そんな状態で言ってしまうものだってある。
ただ、途中からスーッと離陸するSONGで、かっこいいものは多い。
だから、曲アタマからでろうが、曲中であろうが、心中であろうが、
離陸というか、飛距離というか、
この感覚はいくらかの利点にはなってはいるのだろう。
「地下書店」については、いずれまた書きくわえるときが来るはずだ。 |
|
|
(1)
たそがれの地下書店に 一通のメールが届 く
多分もう行かないという 夢のつづき短い言葉
ほつれた翼は 知らない本の
しおりに使って 遠い棚にもどす
(2)
階段を数えてのぼる ありふれた癖だとしても
目の前のたった一段 崖だったら数えられない
なにげなく翼を 捨てたけれど
残ったひとつは このまま忘れたい
(3)
抱きあえぬ魚の姿で 巡り会いはぐれるまで
祝福の雨の拍手に 悪気もなく耳をふさいだ
冷たくしびれた 魚の尾鰭が
まぼろしでも翼に 変われば重い
☆
たそがれの地下書店に 一通のメールが届 く
多分もう行かないという 夢のつづき短言葉
|
|
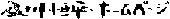
Copyright©2001-2003 Kouhei Oikawa(kohe@music.email.ne.jp)
|