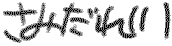
|
| 歌のはなし |
曲名 |
公表作品 |
作詞者 |
作曲者 |
| 014 |
さみだれ川 |
『みどりの蝉』『なつかしいくらし』
|
及川恒平 |
及川恒平 |
|
   |
|
4/4
|
《前奏》
AΔ ≒ EΔ ≒ E6(9) F#m9 E ≒
E AΔ A7 A6 E
さみだれ川の 澱みに うたかたの 夢 浮かぶ
C#m G#m F#m B7
それが 誰の 気持ちやら 逃げるように 掻き消えた
C#m G#m F#m B7 A/Adim E ≒
春の匂い 夏の光 秋の 話 冬の 祈り
E AΔ A7 A6 E ≒
かやの木山の 麓に 空蝉の 影 宿る
C#m G#m F#m B7
それが 時の 姿なら いつになれば 忘られる
C#m G#m F#m B7 A/Adim E ≒
春の匂い 夏の光 秋の 話 冬の 祈り
《間奏》
AΔ ≒ EΔ ≒ E6(9) F#m9 E ≒
E AΔ A7 A6 E ≒
夕焼け町の 通りに 暮れなずむ 歌 よぎる
C#m G#m F#m B7
それは 人の 憧れが 飛べぬままに 酔いどれて
C#m G#m F#m B7 A/Adim rit.E
春の匂い 夏の光 秋の話 冬の 祈り
|
 |
なるべく早い機会にこの歌については書こうと思いながら今日になった。
理由はいくつかある。
ひとつはこの歌がここしばらくの間、ぼくのコンサートのオープニング曲になっていたこと。
つまりは、その程度の重要性を帯びていたことによる。
もうひとつは、〜ていた、と過去形で記したように最近歌わなくなりつつあることである。
正直いって、この歌がわからなくなってきた。
二十数年前に作ったのだか、その当時と同程度に現在わからなくなってきたといったところか。
|
 |
順をおって説明してみたい。
まず、ぼくが四十代になって、歌うことにふたたび集中しだしたとき、
この歌はメインの一曲であった。
なにか理由をあげてみたいと思ったのだが、当然すぎる流れであったとしか言いようがない。
しかし、二十代に作った当時、
この歌はアルバムの片隅に入っていただけの役回りだったのだから、
どうしてわざわざ思い出してまで歌うことになったのだろう。
いや、わざわざ思い出したのではなかった。
歌いたかったが、当時反響の弱さにあきらめて引っ込めていたことが、
記憶の彼方からよみがえってきた。
放送媒体など、『単純即決』の世界にいたぼくには、
この歌を歌いつづける立場になかったといったところか。
つまり、四十代に歌い出したときは、そんな『重責』は微塵もないので、
好きな歌をただ歌えばよかったのだ。
思えば、この行為は「今はこんな気持で歌っています」
という一種の宣言であったのかもしれない。
そして「さみだれ川」こそ、フォークブームの真っ只中にいたぼくと、
ひっそりと横浜というローカルな土地で
また歌い出したぼくをつなぐ歌のひとつだったということだ。
こんな歌を中心に歌いつづけたかったぼくが、結局ながい休止をよぎなくされたのは
「さみだれ川」が歌えないということに象徴されるだろう。
|
 |
ぼくの二十代後半、時の趨勢として、
ニューミュージックと銘打たれたパッケージに入っていなければ
評価の対象になりにくくなっていった。
音も、ギター一本だなんて時代おくれなという声が、ぼくのような弾き語り歌手の、
か細い歌声なんか消してしまうのに、充分な大きさになっていったのだった。
もちろん、そんな時の流れと刺し違える勇気があれば、
またちがった行き方、生き方ができたのだろう。
残念ながら、ぼくは弱虫のひとりにすぎないと、つくづく思い知らされるだけだったのだ。
さて続いて、ここにきてこれを歌わなくなってきた理由を書いてみたい。
と、書きながら、実は明確な答えを用意してあるのでもない。
まあ、この歌が橋渡しの役割りを終えつつあるとも言えるのだろうが、
それだけではなにかしっくりしない。
どうも、今距離をおいているわけは、歌の内容にあるようだ。
この歌に書かれている風景に歌手としてのぼくが、心をゆだねていることに、
ちょっとした違和感を持ち出しているといったところだろうか。
典型的といっていい「ジャパニーズ」が充満している歌詞だと自覚しているが、
演奏部分を含めて、なにかチガウ発想に基づいた歌にどうも変身したいのだと思う、ぼくは…
結局、この歌ともう一度出会って、元気だったかと酒でも酌み交わしたい気分なのだ。
|
 |
|
   |
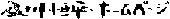
Copyright©2001-2003 Kouhei Oikawa(kohe@music.email.ne.jp)
|