| 日々のこと36 |
無 題 か ら は じ ま っ た 。
|
  |
|
 |
|
『無題』 作詞曲/小室等
いつもいつも
ぼくが君を見ててあげるから、
安心しておやすみ
傷つけあうことに
なれてしまったこの世界
そこでぼくらは 生まれそだった
|
|
|
(C)rokumonsen-factory
|
|
 |
小室等作のこの歌が、シンガーソングライターにとってなぜか気になるのはぼくだけではないだろう。では、なぜこれほどまでにシンプルなこの歌が気になるのか。これほどまでにシンプルだからこそ、気になるといっていいのだけれど。ここに、たどり着いたとき彼は、きっと小さいながらアンドの息をもらしたに違いない。
四半世紀を歌い継がれてきたこの一作品がつきつけている問題は、実は、ぼくらフォーク歌手たちの根源的な部分と思われる。ここで、ちょっとは触れておきたい。
|
 |
白状すると、ぼくは小室の自作詞による曲を他にあまり知らない。そして、六文銭以降の彼の自作詞曲も、不勉強であまり知らない(陳謝)。知り合ったころ、というか、ぼくが彼を知ったきっかけのひとつが現代詩人の作品に曲をつけて高校生向けの新聞に、その譜面を発表していたのを目にしたことだ。おそらく、そんな試みの中で、彼は自作詞を手控えることになっていったように思う。
この作曲家の作品を理解することは、他の誰の歌をそうするより、僕にとっては、ずっと楽なことであった。なぜなら、当時のどんな作品よりも、音符の側には立っていなかったからだ。正確に言うと、単語の持つ音節単位で音符がかかれることを、もしかしたら、意識的に避けていて、文脈にそって曲が書かれていたのが、ぼくを楽にしてくれたのだった。
つまり、彼の手になったそれらの作品群にとって音符は、その詩が本来含んでいた音楽性を、よりあきらかにした結果として並べられていたということなのだった。
|
 |
この技術は、当然もっとフォーク界に普及してもよかったと思うのだが、そうはならなかった。理由は、小室が身に付けていたものは、実はむしろギター少年に手に入りにくいものだったからだ。そうして、その技術を見につけているものは、今度はフォークソングにに近寄らないか、または遠ざかるかしたように思える。
ちよっとばかり、もって回ったが、その技術とは種も仕掛けもない“詩を読むちから”だ。おそらく、小室も当時の先端を走るフォークという音楽に飛びついたとき、見る聞くなしに、そのスタイルを取り込んでみたりもしただろう。ぼくは、残念ながらそんな初期の小室作品は、言ったようにあまり知らない。つまり、それらの作品群をとらえたうえでの判断ではないので、いささか心もとないけれど、そんなにひどく間違えてもいない気がするので、これわを書き出したわけだ。
|
 |
何かを読むひまがあるくらいだったら、とにもかくにもギターを弾いていた時期をすごしたものが、
後に、フォークブームの担い手になっていった。だから、仕方が無いともいえるのだが、作詞もすることになったのだから、彼らには、もうちょっとは既成の歌詞ばかりではなく、詩世界にも目を向けてほしかった。もっとも、気持ちのいい音が鳴ったりすると、つい目を閉じてしまうものだけれど・・・
この詞と曲のバランスの悪さは、どんな大ブームがおきたにせよ、現在にいたるまで、当然このジャンルの歌の宿命的な欠陥としてのこっている。 “おまえの言うほど、問題になっていないじゃないか”と、考えるフォークファンもけっこう多いだろう。
そのわけをここで書くのは、みずからの首をしめているようなものだけど、カキマス。ようするに、このバランスの悪さを許容できたひとが、フォークをささえる一大勢力だったからだ。つまり、このことを問題とした人は、近づかなかったか、ここから出て行ったかしたのだ。そう、たったひとり、小室等を例外にして。オーヴァア(必ず下唇をかむ事!)
|
 |
しかし、言葉がわを安住の地とした人たちも、ちょっとは気がついてもよかった。のちに、オトを詩に取り戻すとかいって、ジャズと偽装結婚するぐらいだったら、もっと、やることはあっただろう。フォークなんて、ミットモナイとか思ったんだろうなあ。当時、どこかのジャズクラブで、ぼくは、フォーク歌手のくるところじゃないと言われたこともあったのてすよ。どちらから見ても、チャンスを逸したといえる。もっともチャンスには見えなかっただろうけれど。
ところで、その後のフォーク系作詞者たちは、どうなったかというと、どうにもなっておらんのです。自浄装置をもたないまま、リバイバル(とは言っても年代的に非常にうすい)してしまったから、あいかわらず、再生産しか生き延びる道がない。 むしろ、新しい試みは、あっフォークじゃない、とかつぶやかれそうだし・・・
ついでに言うと、フォークソングの批評も、歌詞に深く分け入ったものは、意外に少ない。類型的な時代論に終始ししているケースが多い気がするが、どうだろう。だいたい、正確で“愛のある”批評が作品を育てるのは、スポーツだって、音楽だって、どんな世界でも当然なのにね。こんな言い方は絶望的にすぎるので、まだフォークには、ほそーい道はあるかもしれないとでも言っておきマスカ。
|
 |
ついつい興奮してしまった。話をもどそう。小室等が、『無題』を書いて、ふと得た安堵感の正体は何か。それは、現代詩など文学系が培ってきた、レトリックの嵐から脱出した記念碑がこの『無題』だったからだ。作品発表当時、、失礼ながら彼自身にも、この歌の重量を計りかねていたようにも思う。それでも、無意識に近い状態でも、ほっと一息つける気分になったのは、たしかだったろう。ただし、こうしたた言葉と音の問題は、ひとりでなんとかするには小室をもってしてもデカスギルのだ、と言わせてもらいたい。
彼は、肩からそっと、その大きな荷物を降ろした。そうして、ぼくの耳元でささやいたのだ。『で恒平、ちょっと、この荷物かわりに持ってみてくれる?』『いいよ』とかなんとか、かるーい気分で、それを持ったぼくは、じきに腰を痛めた。十数年の治療期間が必要になったのだった。
|
 |
それでも、とぼくは思う。あのレトリックのボタ山を眺めながら、もしかしたら、またタンコーが必要な時代が訪れて、もうひとつ、別のレトリックのボタ山をこしらえることになるのかもなあ、と。
ところが、と、最後にもう一ひねり。それを、とうの小室等が望んでいるらしい。
|


 |
ここで、終りと思ってはいけない、まだ続きがアルノデス。フォークソングの特徴として最大級のものは、間口の広さ。(専門的な音楽教育をうけていない僕が、こうして歌っていられる現実をミヨ!)言葉を代えれば、アマチュアリズム。しかし、あなどってもらっては困る。
たとえば、マラソンを走りぬいたその後に飲むいっぱいの水にまさる“味覚”をぼくは知らない。グルメとは食物という観念での、衰弱化を意味する場合もあると、自分への“やや”反論として示しておきたい。
|
 |
|
2003年夏  舞台裏 舞台裏 |
|
|
 
|
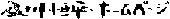
Copyright©2001-2003 Kouhei Oikawa(kohe@music.email.ne.jp)
|